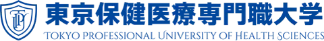コラム
【コラム】不登校の原因や対応とは?
こんにちは!東京保健医療専門職大学入試広報部です。
今回のテーマは「不登校」についてお話しします。
不登校は年々増加しており、社会問題となっています。2023年度は過去最多34万6482人に上がったことが文部科学省の調査でわかっており、前年度より4万7434人多く、30万人を超えたのは過去初めてとなりました。(2024/10/31「朝日新聞」より)
コロナ禍で生活や教育環境の変化もあり、子どもたちにとって大きなインパクトが背景にあるようです。また、不登校はSDGsにおける教育や不平等の目標にも関わる問題であり、定義や現状を確認しながら、対応やサポートをおこない、安心して教育が受けられる環境を整える必要があります。
「なぜ不登校になってしまったのだろう…」とつい考えてしまいがちですが、不登校になってしまう原因は様々です。不登校への向き合い方について解説します。
1、「不登校」とは?
「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景によって、登校しないあるいはしたくてもできない状況にあるために、年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。(出典:文部科学省-不登校の現状に関する認識)
2、「ひきこもり」や「長期欠席」との違い
「不登校」と間違われやすい言葉として、「ひきこもり」や「長期欠席」があります。
これらの違いについて説明します。
「ひきこもり」は、6カ月以上にわたる長期間、家でふさぎ込んでいる状況を指します。
「不登校」は学校に行かない高校生までの子どもを指すのに対し、「ひきこもり」はそれ以上の年齢の方を含む点で異なります。
また、「長期欠席」は、不登校の定義に含まれなかった病気や経済的理由などにより、学校に通えていないことを指し、やむを得ず欠席している状況です。
3、不登校によって起きる問題
不登校によって起こりうるリスクや問題は大きく以下の2つがあげられます。
①自己肯定感の低下
周りの友人たちが学校へ通っているにも関わらず、自分ができていないことに自信をなくしてしまうことがあります。何かにチェレンジする意欲がなくなってしまったり、周りの目を気にして外出することが減ってしまったりと、自己肯定感が低下することであらたな問題に繋がってしまう可能性があります。
②コミュニケーション機会の減少
学校での経験や学びはこれから社会人となる上で大切な土台とも言えますが、学校に行かないことで、人と交流する機会が減り、集団行動の中で学んでいく協調性や多様性などの価値観を得る機会が減る可能性があります。

4、不登校の子どもにあらわれる症状
子どもにとって、“学校に行きたくない・行けない”ということを言葉で伝えることはなかなか難しいことです。
初期症状は身体の不調という症状としてあらわれる場合も多く見られます。
・頭痛
・吐き気
・腹痛(トイレにこもってしまう)
・登校前夜に眠れない
・布団を被ったまま泣いてしまう、布団から出られない
・一旦家を出たけれど、また家に戻ってきてしまう
・玄関に立ちすくんだまま動けなくなる など
学校には行きたいけど行けないと、なぜ自分はこうなってしまったのか理由もわからず困っている子どもも多くいます。体調だけでなく、子どもの心の変化にも気づきにくいこともあります。
時期としては、GW明けや夏休み明けなどの長期休暇明けや、進級でクラスが変わったり、学級委員や席替えなどの環境変化で影響を受けるときがあります。
5、受診の目安
不登校だからといって皆が受診しなくてはいけないわけではありませんが、頭痛や腹痛などの身体症状があるときには、小児科などかかりつけ医に相談するとよいでしょう。
心の状態が気になるときや集団生活で過ごしにくさがあると感じたときには、児童精神科や教育支援センター(適応指導教室)などに受診していただくものひとつの方法です。
不登校の関わり方に関して相談相手も少ないため、保護者が一人で悩んでいるケースも多いです。悩んでいる間に家庭内のいさかいが増えたり、状況がさらに悪化することもあるため、気軽に相談できるところが欲しいというときが受診のきっかけと言えるでしょう。
治療が必要な場合は、治療の提案や他の機関への紹介をする場合もあります。
6、専門家による治療
不登校といっても、ベースに発達面や精神面での特性がある場合とそれらが全くないケース、いじめや担任との不和などの環境要因がある場合等様々です。それぞれに応じた支援に枝分かれしていきます。発達段階にある子ども、思春期の生徒や学生が対象になりますので、特に個別性が高い領域と言っても過言ではありません。
例えば児童精神科を受診した場合、はじめての診察では子どもの様子を問診したり、必要に応じて心理専門職や作業療法士がWISC等の心理検査を行うこともあります。睡眠リズムを整える、心の病の症状が見られた場合には、心理専門職によるカウンセリング・SSTなどを行なうこともあります。
勉強でつまずいている場合は、作業療法士などの専門家が何を苦手に思っているのかを評価把握・指導をするとともに、何が得意なのか、得意なことで苦手をカバーできないかを重要視した関わりをし、心のケアをしつつ、活動の場を広げるようにサポートします。よく、WISCで得られたIQの結果を重く受け止める保護者もいらっしゃいますが、それはひとつの参考資料でしかありません。成長とともに変化もしますし、他者に数値で評価されるという取り組み自体に後ろ向きなお子さんであれば検査結果など参考にもならないことだってあるのです。誰にでも苦手な部分はありますが、重要なのはそこばかりに焦点を当ててなんとかしようとするのではなく、出来ていることや好きなこと、取り組みやすいことに目を向けて認めてあげることと、得意で不得意をどう補填できそうかを考えていくことです。そして、これらの情報を関係者の間で共有し、共通認識をもってアプローチすることが重要となります。悩みを抱える保護者や学校関係者の相談窓口、調整役を担うというのも、作業療法士の仕事の一つなのです。
学習面を気にされる保護者は多いですが、まずは野菜の栽培・クッキング・お楽しみ会・e-sports大会の開催など仲間と何かをする楽しさ達成感、充実感を得たれるようなプログラムを実施するところから信頼関係を構築し、治療的に関わって自信を取り戻していくことも多いです。特に作業療法士は個別性の高い対応を臨機応変に検討する職種ですので、不登校が増加する中、今後活躍の場は大きく広がっていくことが予測されます。

このように、小・中・高等学校の不登校が急増していることは喫緊の課題と言えます。
学び方が多様化する昨今において、不登校の解決は、「再び学校に通うこと」が目標ではなく、「将来的な社会生活における自立」を目指すことが基本的な考えとなっており、保護者や学校は共通認識を持って取り組むことが大切です。
そのためには、専門機関や専門家とも連携し、地域や民間施設と協力しながら支援していく姿勢を持つことが必要です。
監修:東京保健医療専門職大学 教授 大澤彩(作業療法士)